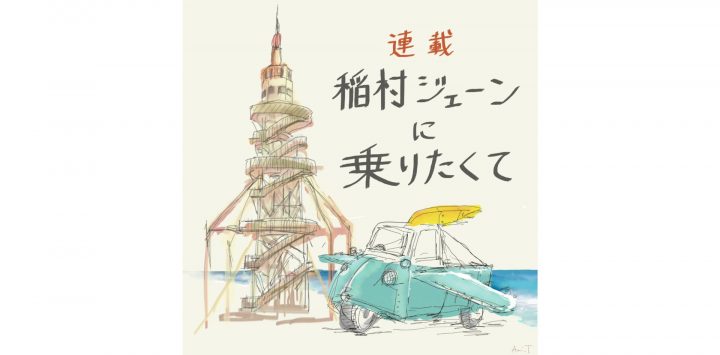そこへ行かなければ出会えない景色がある! いざ、大山詣り

(TOP画像)神奈川県立図書館 神奈川県郷土資料アーカイブより
神奈川県西北部、丹沢大山国定公園に位置する大山。地理的な条件から山上に雨雲をたたえていることが多く、別名「雨降山(あめふりやま)」、転じて「阿夫利山(あふりやま)」とも呼ばれます。豊作を願う農民たちは、雨乞いの祈りを捧げる山として古くから敬ってきましたが、その人気が盛り上がったのは江戸時代のこと。江戸の人口が100万人ほどだった時代に、その1/5にあたる約20万人が1年間に大山を訪れたというから驚きです。

*五雲亭貞秀「相模国大隅郡大山寺雨降神社真景」 画像提供:神奈川県立歴史博物館
都市部からの交通アクセスがよく、初心者でも気軽に登れる大山は、近年改めて注目が高まっています。2015年には『ミシュラングリーンガイド』で“大山”が星1つ、“大山阿夫利山神社からの眺望”が星2つで掲載されました。
数千年の昔から人々に崇められ、独自の文化や風習が育まれてきた大山。大いなる自然に抱かれつつ、日本の歴史と文化を感じる小旅行———大山詣りに出かけてみませんか。

*山頂付近からの展望
大山には登山ルートがいくつかありますが、阿夫利神社下社までケーブルカーで行き、標高1,252メートルの山頂を目指すルートを登ってみました。
登る前にまず立ち寄りたいのが「良弁滝(ろうべんだき)」です。
大山の中腹にある大山寺(後述)を開いた良弁が、入山の時に水行を行ったと伝わる滝で、大山詣りが盛んだった江戸時代の浮世絵には、ここで水垢離をする参拝者の様子がしばしば描かれています。

*歌川国芳「大山良弁滝之図」 画像提供:神奈川県立歴史博物館
良弁滝へは、小田急電鉄・伊勢原駅北口から神奈川中央交通バスに乗り、「大山ケーブル」バス停の1つ手前「良弁滝」で下車。赤い開亀橋を渡ってすぐです。

滝の高さは約4メートル。大山川の改修もあり、滝の規模は小さくなりましたが、今でも冷たく清らかな水が流れ落ちています。

落ち口が龍頭になっているので、なんとなく霊験あらたかな感じがします。

傍らに建つ開山堂には、良弁僧正42歳の時の像と、『大山寺縁起絵巻』で語られた伝説に基づく「猿が金鷲童子を抱いた像」などが安置されています。

大山ケーブルカーの始発駅へと続く「こま参道」は、こちらから。参道沿いには食事処や土産物屋が並んでいますが、これは帰りのお楽しみにとっておきましょう。

362段の階段を登ること約15分で、大山ケーブル駅に到着。
登山道も整備されているので歩いて登ることもできますが、ここは無理せずケーブルカーを利用しました。

大山ケーブルカーの開通は1931年。戦争による鉄材供出のため1944年に廃止となりましたが、1965年に復活開業して現在に至ります。
2015年に全面リニューアルを行い、乗り心地や安全性の向上はもちろんのこと、グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな車体にグレードアップ! 朝9時の始発から20分間隔で運行しており、ハイシーズンにはさらに増便されるほどの人気です。

出発して間もなく、後方の視界が開けて車内に歓声が上がりました。平野の先でキラキラ光っているのは、江ノ島を浮かべた相模湾。海からそう遠くないことに気づいてちょっと驚きます。

途中の大山寺駅で下りのケーブルカーとすれ違い。鉄道ファンには嬉しいシーンです。
ここで途中下車することもできます。

約6分で阿夫利神社駅に到着。駅は標高約700メートルにあるため、山麓とは違うひんやりとした山の空気を感じます。

阿夫利神社下社の拝殿まで続く参道には、奉納された石灯籠がずらり。これを辿って行けば、初めて訪れる人でも道に迷うことはありません。

途中の広場には茶屋が並んでいます。そば、うどん、ラーメンなどの軽食からお団子、ソフトクリームなどのスイーツまで。メニュー豊富に揃っていますが、こちらはお参りしてからのお楽しみにとっておきます。

下社の拝殿までは、さらに108段の石段を登ります。

階段を登りきったあたりで振り返ると、眼下には素晴らしい景色が広がっていました!

雨上がりの空気の澄んだ日には、相模湾に浮かぶ江ノ島や三浦半島、さらに房総半島までが一望。夜景の素晴らしさでも知られ、夏の納涼シーズンや秋の紅葉ライトアップ期間には、ケーブルカーの「夜景運転」が期間限定で行われます。

大山阿夫利神社の創建は紀元前97年頃と伝わります。鎌倉時代以降は、源頼朝をはじめとする武家の崇敬を受けました。大山詣りが一大ブームとなるのは江戸時代に入ってからのことで、参道には170軒もの宿坊が建ち並び、庶民の参詣客で大いに賑わったようです。

拝殿の前で「ごま木」が焚かれていました。備え付けのごま木(初穂料200円)に願い事と住所・氏名を記入し、神火の灯った神爐で炊き上げることで、大願成就を願う作法です。静かに立ち昇る煙に向かって手をあわせ、自分自身と家族の平穏や健康を祈りましょう。

拝殿の右側に「大山名水入口」とあります。入ってゆくと、拝殿地下から湧き出る御神水「神泉」が汲める泉がありました。神泉は殖産・長命延寿の泉として知られ、大山の銘酒にも使用される名水です。誰でも自由に汲むことができるので、登山中の水分補給用に汲んでゆく方も多いようです。容器がない方のためにペットボトルも販売しています。

拝殿左奥にある「登拝門」をくぐり、いよいよ登山開始。いきなり急な階段なのでドキっとしますが、主祭神を祀る本社へはここからさらに1時間半ほど登ります。

階段を登ると、その先はひたすら岩の多い登山道になります。初心者レベルとはいえ“登山”なので、トレッキングシューズなどの装備は必須です。
本社のある山頂は「二十八丁目」。「◯丁目」と記された道標を数えながら一歩一歩登っていきます。

八丁目あたりにある「夫婦杉」は、左右ともに樹齢500〜600年。大山にはこのほかにも苔むした巨木がたくさんあり、アート空間のようにも感じられます。

相模湾方向に視界が開けたポイントで一休み。
広い平野に目を凝らすと、横浜みなとみらいのビル群が小さく見えました。さらに伊豆半島や大島が見渡せるポイントもあるので、景色を楽しみながらゆっくり登りましょう。
二十丁目にある「富士見台」は文字通り富士山の絶景ポイントですが、残念ながらこの日は富士山を拝むことはできませんでした。
ところが!

山頂近くまで登ったところで雲が移動し、富士山が姿を現しました。
まさにミシュラン級の展望です!

そしてついに、山頂に到着。下社から1時間30分ほどの登山でした。

まずは無事登頂できたことを感謝して、阿夫利神社本社を参拝。

山頂にはベンチやテーブルが用意されているので、持参したお弁当を青空の下で広げるのはとてもいい気持ち!
また、山頂の茶屋では山菜そば、豚汁などの軽食がいただけます。頑張って登ったご褒美に、あたたかなスープがことのほか美味しく感じられました。

下山は、相模湾と広々とした関東平野を眺めながら歩くコースです。

訪れたのは11月初旬。頂上付近では木々の紅葉がはじまり、青空とのコントラストが美しい季節です。

1時間ほど下って「見晴台」に到着。ここは横浜〜都心方面まで見渡せる絶景ポイントです。
下社から直接ここを目指すルートもあり、見晴台まで30分ほどで歩けます。スニーカー程度の軽装でもOKなので、大山の絶景を気軽に楽しみたい方におすすめです。

売店などはありませんが、軽食や飲み物を用意してゆくと、ちょっとしたデイ・キャンプ気分が味わえそうです。ベンチとテーブルがたくさん並んでいるので、下山してきた方が一息入れるのにもぴったり。

見晴台を過ぎると、なだらかな下りの山道になります。キラキラ光る木漏れ日を満喫!

水が流れ落ちるかすかな音が聞こえる気がする…と思ったら「二重社」の小さな祠が目に入りました。

すぐ脇に流れ落ちている「二重滝」は、かつては修験者の行場であったといわれています。
ここから下社までは5分ほど。わずかな距離なのに、景色も喧騒も別世界のように感じます。

阿夫利神社下社に戻ったら、境内にある「茶寮 石尊(さりょう せきそん)」にも立ち寄ってみてください。ミシュランで星を獲得した絶景はもちろん、大山の名水で淹れた抹茶やコーヒー、オリジナルのスイーツなども楽しめるおしゃれなカフェです。

設計を手掛けたのは、建築家・堀部安嗣氏と国の重要文化財修復に携わる宮大工・内田幸夫氏。座敷からテーブル席、縁側、テラスのカウンターへと続く開放感のある店内は、どこに座っても大山の自然と風が心地よく感じられ、思わず長居してしまいそうです。

きな粉やあんこを使ったガレット、伊勢原の老舗茶問屋「茶加藤」の抹茶パウダーを振りかけた抹茶ティラミスなど、見た目におしゃれで食べて美味しいメニューが充実。阿夫利神社の御神水で淹れたコーヒーは、飲むだけでご利益がいただけそうです。

《茶寮 石尊》
[営業時間]9:30〜17:00(ケーブルカー運行終了の30分前まで)
[電話]0463-94-3628
[定休日]不定休
ケーブルカーで山麓まで下りてしまう前に、もう1カ所立ち寄りたい場所があります。
奈良の東大寺を開いた良弁僧正が755年に開山した「大山寺」です。

本堂は、明治の廃仏毀釈によって破壊されたものを、全国の信者たちの寄進によって明治18年(1885年)に再建されたものです。本堂周辺に施された彫刻の数々が素晴らしく、当時の職人たちの高い技術と魂を込めた仕事ぶりが伺えます。

阿夫利神社下社から徒歩で下山する場合、「男坂」を通ると大山寺に立ち寄ることができないのでご注意ください。

参道は紅葉の名所としても知られています。山頂より標高が低いため、紅葉にはまだちょっと早いようでしたが、整然と並ぶ仏像の姿が美しく、心が洗われる思いでした。

大山名物で忘れてはいけないのが、大山の名水で仕立てた豆腐です。こま参道などに並ぶ茶屋や食事処では様々なスタイルの豆腐料理がいただけるので、ぜひ味わってみてください。
「とうふ処 小川家」は、参詣者のための宿坊からはじまった老舗の一軒。現在は様々なとうふ料理を会席スタイルで提供しています。

ごま豆腐、湯葉といった定番料理にはじまり、栗・柿・きのこなど季節の素材を取り入れた白和え、豆乳湯豆腐、グラタン、豆乳を使った杏仁豆腐といったオリジナリティ溢れる料理まで。料理はどれも丁寧な仕事が感じられ、豆腐料理の奥深さに驚きます。
ご主人は「豆腐はシンプルだから、いろいろ工夫しないとね」と笑いますが、そのシンプルさをいかした多彩な味のバリエーションは「さすが」としか言いいようがありません。季節ごとに料理の内容が変わるので、何度訪れても違った美味しさに出会えそうです。

《とうふ処 小川家》
[営業時間]11:30〜16:30
[電話]0463-95-2270
[定休]不定休
美味しい大山に続いては、大山土産です。江戸時代中期発祥の「大山こま」を現在も作り続けている金子吉延さんのお店をのぞいてみました。

大山こまの特徴は、心棒が太く、どっしりと安定感のある形状と、藍・赤・緑など色彩豊かなろくろ模様にあります。「よく回る」ことから、「人生が滞りなく廻る」「金運がついて回る」など縁起が良いことと結びつけられ、縁起物としても親しまれています。
《金子屋支店》
[営業時間]8:00〜17:00
[電話]0463-95-2262
[定休]不定休

削り出しから彩色まで、一つひとつ丁寧に仕上げてゆく工程は“熟練の職人技”そのもの。タイミングが合えば、店先の工房で金子さんがコマ作りを行っている風景が見られることもあります。

店頭には直径12センチの特大こまから3ミリほどの小さなコマまで、15種類ほどのコマが並んでいます。すべて手作りなので、色や形の微妙な違いをじっくり確かめ、お気に入りのこまを選びましょう。

大山こまの他にも、大山にはコンニャクやわらび餅など、美味しい大山土産がいろいろあります。参道を歩きながらお土産を探すのは、今も昔も変わらない大山詣の楽しみのひとつです。