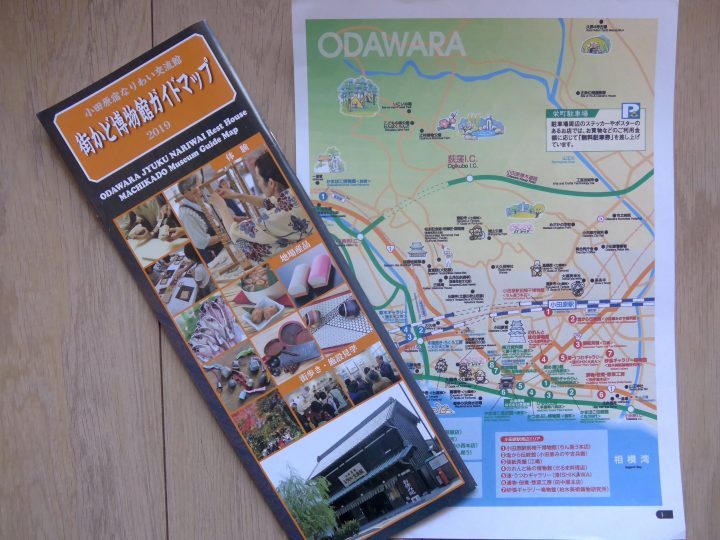Double Planet 第11話

Double Planet
第11話「どうか冷めないで」
青野サトル(フルタジュン&神田陽太/レディオ湘南パーソナリティ)
「私と、ここで夜まで待てるなら」
田丸さんが放った一言は、僕の弱い部分を全方位的に打ちのめした。もしかして頭の中を読まれているのではないか。お金もないし、夜ご飯までには帰りたいと思っていた自分が情けなかった。田丸さんと向き合わないといけないのかもしれない。ちゃんと向き合わない限り『空とパズル』のことを教えてもらうことはできないのか。僕が答える番だった。
「え、そのつもりだったけど」
格好をつけてしまった。最初から夜までいるつもりだったと口走っていた。それを聞いた田丸さんは笑いをこらえるように「そっか」と言った。またしても頭の中を読まれているような気がした。

「今夜、空に星が出るのを待つの」
田丸さんはわずかに明るさが残る空を見上げて言った。そもそも夜の定義ってなんだろう。何時から夜が始まって、何時に夜が終わるのだろう。そして、星はいったい何時に出るのだろう。分からないことだらけだった。スマホを取り出してネットで調べたら正解らしきものが出て来るかもしれない。けど、今夜だけは、その正解はあんまり意味がないような気がした。
ここで星が出るのを田丸さんと待つ。
おそらく答えはそこにしかない。
黙ったまま波の音を聞きながら、田丸さんと海を見ていた。
海風が容赦なく吹いてきて、体が冷えてきた。
こんなことになるなら上着を持ってくればよかったなと思った。
けど、江ノ電に乗った時、まさかこうなるなんてことは想像できなかったわけで。
今は前向きにこの寒さと状況を受け入れるしかない。
ふと、額に妙な冷たさを感じた。
雨粒だった。
それを皮切りに、ポツポツと雨が降り始めた。
海面に雨粒が溶け込んでいく。
「雨だ?! 降って来ちゃった……」
オロオロする僕の横で、田丸さんはスクッと立ち上がった。
「帰るの?」
「雨宿り」
田丸さんはスタスタと砂浜を歩いて道路の方へ戻っていった。僕は飼い犬のように田丸さんのあとを追いかける。

「どこに行くの?」
「隣の駅」
鎌倉高校前の隣は七里ヶ浜だ。
どうやら駅の近くにはセブンイレブンがあるらしい。
雨はさっきよりも強くなっていた。僕らは早歩きで道路を歩いていた。
雨雲が空を覆えば、空に星が出ないことぐらい僕にもわかる。まったくツイていない。溜息が漏れそうになる。
「嫌なら帰ってもいいよ」
またしても田丸さんは僕の心を読んで来た。
「え、帰らないけど」
僕も負けていない。強がるのに必死だ。男とは強がる生き物なのだ。
必要以上に早歩きのスピードをあげて、田丸さんを追い抜かしてみた。
自分の幼稚さに眩暈がする。
いったい僕は何をやっているんだろう。いったい何と闘っているんだろう。
思えば、学校以外の場所で女の子と並んで歩くことさえ初めてだったりする。
そんな照れを気づかれたくない気持ちもあったりするのだろうか。
すると、今度は田丸さんが小走りで僕を追い抜いていく。
「お・さ・き・に!」
彼女の何かに火をつけてしまったのか、田丸さんは結構本気のスピードだった。僕と同様に負けず嫌いなのかもしれない。僕は走って田丸さんを追い抜いてみた。
「あ・と・で・ね!」
田丸さんはさらにスピードを上げてきた。こうして、僕らは抜きつ抜かれつのデッドヒートを繰り返しながら(楽しみながら)目的地のセブンイレブンにたどり着いた。
庇の下に入るなり、笑い合った。
びしょ濡れになったけど、走ってきたせいで体から熱を発しているのが分かる。
雨の中を走るのがこんなにも楽しいとは意外な発見だった。
果たして一人で走っても楽しいのだろうか。もしかして田丸さんと走っていたから楽しかったのだろうか。湯気がたちのぼる体の熱が冷めるとどうなるのか、だいたい予想が付いた。
「冷えたら風邪ひいちゃうかも」
田丸さんがその心配を口にした。
僕はそれに抗う一つの方法を思いついた。
「だったら、冷まさなければいいんだ」
「え?」
僕はその場で反復横跳びを始めた。体力測定でやるアレだ。もちろん冗談だった。田丸さんが笑ってくれるんじゃないかと思ったからだ。どうして笑わせたいと思ったのだろう。どうして笑っている顔が見たいと思ったのだろう。けど、田丸さんから笑い声は全く聞こえてこなかった。チラッと顔を見ると、何かを考え込んでいるようだった。
「ごめん。つまらなかった…?」
「ううん。その発想、すごくいいなと思ったの」
笑わせるどころか、なぜか感心されてしまった。
「冷めることを嘆くんじゃなくて、冷まさないことを考えるという発想はすごい」
僕は褒められることに慣れていない。どんなリアクションをすればいいのか分からない。
田丸さんは、何かを見つけたようにどんどん饒舌になっていく。
「つまり、こういうことでもあると思うの。雨雲で空に星が出ないんじゃなくて、星はどこにも行かないしずっと宇宙にあるの。何億光年前から、消えたりなんかしない。だから、私たちは待つの。待ち続ければ、星は必ず見えるの。動き続ければ体の熱が冷めないように」
一見、彼女は堂々としているから分からなかった。でも、雨雲に覆われた空が不安なのは同じだったのだ。僕の愚かな反復横跳びが、彼女の不安を少しでも取り除けたのなら本望だ。
一応、財布の中身を確認してみた。やはり小銭しか入っていない。着替えのためのシャツは買えそうにない。
「買ってくるね」
「えっ」
田丸さんは、そう言い残すと店内に入って行った。またしても心の中を読まれたのかもしれない。彼女がシャツを買って帰ってきたら、僕はどうしたらいいのか。
相変わらず、雨は降り続いている。
けど、今夜は何があっても星が見えるまで待ち続けてやる。
僕はそう決めていた。
戻ってきた田丸さんの手にはコーンスープの缶が二本握りしめられていた。
「一本あげる」
「え、いいの?」
目の前に差し出された缶を右手で受け取った。
その瞬間、コーンスープの缶が放つ熱でかじかんだ手がじんじんした。
熱は体中を駆け巡り、じんわりと心まで温かくなった。
この熱の一部は、さっきまで握っていた田丸さんの熱かもしれない。

その夜、僕らは星を見た。
《つづく》
*バックナンバーはこちらからご覧いただけます。