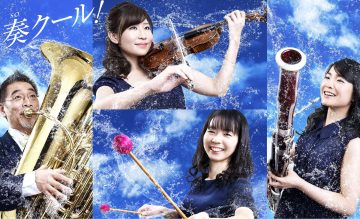『モネ それからの100年』
アーティストトーク開催
横浜美術館で「モネ それからの100年」が開幕しました。クロード・モネ(1840-1926)といえば、日本においても人気の高い画家のひとり。本展は、モネの絵画25点と、後世代の26作家による66点とを一堂に展覧し、両者の時代を超えた結びつきを浮き彫りにしようという試みです。
開幕初日である7月14日(土)、館内円形フォーラムにおいて、出品作家2名と学芸員によるアーティストトークが開催されました。
登壇アーティストはこちらのお二人です。

水野 勝規(みずの かつのり)
1982年三重県生まれ。2005年名古屋造形芸術大学美術学科総合造形コース卒業。2008年京都市立芸術大学大学院絵画専攻構想設計修了。近年の主な個展に「ライトスケープ」(愛知県美術館、2011年)、「reflections」(「MOVING 2015」京都芸術センター、2015年)、「non-fiction」(GALLERY CAPTION、2016年)など。「水の情景―モネ、大観から現代まで」(横浜美術館、2007年)出品。
 湯浅 克俊(ゆあさ かつとし)
湯浅 克俊(ゆあさ かつとし)1978年東京都生まれ。2002年武蔵野美術大学油絵学科(版画コース)卒業。2005年ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修士課程版画科修了。近年の主な個展に「魂の自然な動きはすべて物質における重力の法則と類似の法則に支配されている」(YUKI-SIS、2017年)、「宙・風・景」(MYD Gallery、2018年)、「Trace of Time in Thought」(Northern Print、2018年)など。「魅惑のニッポン木版画」(横浜美術館、2014年)出品。
前半は、アーティストがこれまでの創作活動を自ら紹介するレクチャーからスタートしました。

水野氏は、日常的に出会う風景をビデオカメラでスケッチするように撮影することから創作活動をスタート。当初から水面に映る「虚像」に興味を持ち、ビデオカメラを固定して定点観測するように作品を制作してきました。
映像作家という性質上、作品の制作・展示はテクノロジーの進歩に影響されることに触れつつ、画面が4:3からハイビジョンの16:9へと移行したときは「これは日本画を彷彿とさせる画角イメージだ」と感じたそうです。
水野氏がモネの作品に強く惹かれたのは、直島の地中美術館に展示された『睡蓮』を見たとき。自然光が降りそそぐ白くシンプルな空間で作品に対峙したことで、時間と光の変化によって作品の見え方も揺れ動くことに「モネがやりたかったのはこれか」と腑に落ち、「自分にもできないだろうか」と思ったそうです。

湯浅氏は、美術大学卒業後のロンドン留学を皮切りに、世界各国で創作活動を行ってきた版画家。大型作品を制作する際もプレス機は使わず、ひたすら版木を彫り、バレンを使って1版ずつ刷り重ねる作業を大切にしているそうです。
写真として撮影した画像を版木に彫り、時間による変化を想像しながら少しずつ色を変え、刷り重ねてゆく作品は、モネの世界に通じるものを感じさせます。
「いろんな場所へ行き、風景を見て、撮影して、作品を制作する。出かけるのが面倒なときもありますが(笑)、いろんなところへ出かけて行かないと、自分は作品が作れないのです。場所が変わっても手法は変わらないのですが、自分の中に何かしら変化が必要なのかもしれません」
後半は、主任学芸員・松永真太郎氏の進行による鼎談となりました。

松永 今回は「モネ」というキーワードからお二人に新作も出品していただきましたが、ご自身の創作とモネとの間に「関連性」のようなものはあると感じていらっしゃいますか。実際に展覧会会場をご覧になっての率直な感想をお聞かせください。
水野 今回、自分としては珍しく音声ガイドを利用してみたのですが、モネの生涯の物語を知ることができたのが収穫でした。モネはたまたま出会った情景に惹かれ、その気に入った場所で連作に取り組むことが多かったようですが、「僕も同じだな」と思いました。モネの考え方は、画家というより写真家や映像作家に近い気がします。実際の風景をリアルに描くのではなく、視覚として捉えた情報を表現しようとしたのではないでしょうか。
松永 「映像」というメディアが生まれたのは1895年。モネは「絵画」というメディアの中で時間表現を追求し、それが1880年代から取り組んだ連作につながったのかもしれません。時間の推移と、それによる色の変化を絵画で表現し得るのか。追求途上で映像という新しいメディアが登場しますが、それを使わず、睡蓮というモチーフを、我々の身体感覚に刻まれた時間的な経験を意識しながら表現した。モネの作品を見ることは、大スクリーンの映像を見る感覚に近いのかもしれませんね。

湯浅 パリは人が多くて苦手ですが(笑)、唯一、オランジュリー美術館だけは好きでした。皆さんもご存知のように、『睡蓮』の大装飾画を展示するために作られた美術館です。ここで『睡蓮』を見た時、これは平面というよりインスタレーションのようだと感じました。空間そのものがアートになっていて、とても好きな場所です。
自分も平面にこだわりたい、という思いがあるので、平面を追求したモネの世界観には共感できます。
松永 今回の展覧会では「モネ対現代作家」という、作家の関係を1対1でつなぐ手法をとってみました。改めて会場を回ってみて気づいたのは、モネではなく、現代作家の作品同士を結んで比較する、という楽しみ方です。そこで、お二人にお互いの作品に対する印象を伺ってみたいと思います。
お二人には、RGB、つまり赤・緑・青の三原色を混合して色彩を生みだす共通した技法があります。版画と映像ではメディアが異なりますが、同じプロセスでイメージを作り上げていることについて、いかがお考えでしょう。
湯浅 確かに、共通するものがあると思いました。版画と写真は源流が一緒で、メディアとしては同じ家系図の中にあるといえます。ただ、写真や映像との決定的な違いは、版画は一度サイズを決めたら絶対に変えられないことです。写真や映像は、調整が必要ではあるけれど、スクリーンやモニターを使うことでサイズを変えることができます。でも版画は、10メートルの作品を作りたければ10メートル彫るしかない。大きければその分時間がかかります。そして、自分にとってはそのプロセス、時間自体が重要な気がするのです。
一方で、映像は現地に行って準備を整えた上で撮影するので、やはり時間に強く関わる作品なのだと思います。
水野 湯浅さんの、ライトボックスを使った『RGB』という版画作品を見て「昔の液晶テレビってこんな感じだったな」と思い出しました。それは現象として興味深いことです。人間の目は情報処理能力が高いので、かつて見たことのあるモノに紐付けようとします。僕は映像作家なので、液晶テレビに見えてしまったのでしょう。

松永 改めて気づいたのですが、お二人ともモノトーンの作品からスタートしているのですね。今回は「色彩画家・モネ」との結び付きを浮き彫りにする切り口だったのですが、お二人の作品に色がついていったのには、どういった創作の変遷があったのでしょう。
湯浅 僕は色を使うのが非常に苦手で、はじめはどう使ったらいいかわかりませんでした。ルールを決めて、やり方を決めればできると思い、まず印刷インクの「CMYK」を使ってみました。アイデアは良かったのですが、それを水性木版画でやるのはなかなか大変なんです。インクジェットのデジタルプリンタならインクの色が決まっていますが、水性木版画は自分で色を調合しなければなりません。どのくらいの濃度で重ねればいいのか、という検証に時間がかかりましたね。でもその方法を確立することで、ようやくカラーになったというわけです。呪縛が解けた、という感じでしょうか。

水野 僕は、今でもカラーよりモノクロの方が好きです。普段、僕らが見ている映像はカラーですが、これをモノクロに置き換えた、つまり余分な情報がなくなった映像が最初に作ったモノクロの作品です。僕はリフレクションを撮っているので、余分な情報を取り除くことで、虚像が実像のように見える、という印象に興味があったのです。
ただ、ずっとモノクロで作っていくと飽きてくる、というか単調になってくる。それを打開するために、カラー作品を作るようになりました。

松永 今回の展覧会では、多様性を表現できたと思っています。現代アートをご覧になると「こっちはわかる」「こっちはピンとこない」と思うことがあるかもしれません。けれど個人の感覚による多様性はあって当然だし、それがアートの世界です。多面的な見方を許容し、異なる見方の存在を提示していくことも美術館の役割だと思っています。それが今回の展覧会のキャッチコピー「わたしがみつける新しいモネ」で表したかったことですので、ぜひ本展をきっかけに「あなたのモネ」を見つけてください。
本日はありがとうございました。
《次回アーティストトークのご案内》
日時 7月29日(日) 14:00〜15:30 *開場13:30
会場 横浜美術館円形フォーラム
登壇アーティスト 小野耕石、児玉麻緒
聞き手 松永真太郎(横浜美術館主任学芸員)
定員 80名(事前申込不要、先着順)
参加費 無料
モネ それからの100年
会期:2018年9月24日(月・振休)まで
会場:横浜美術館
休館日:木曜日(8月16日は開館)
開館時間:10:00〜18:00 *9月14日(金)、15(土)は20:30まで
(入館は閉館の30分前まで)