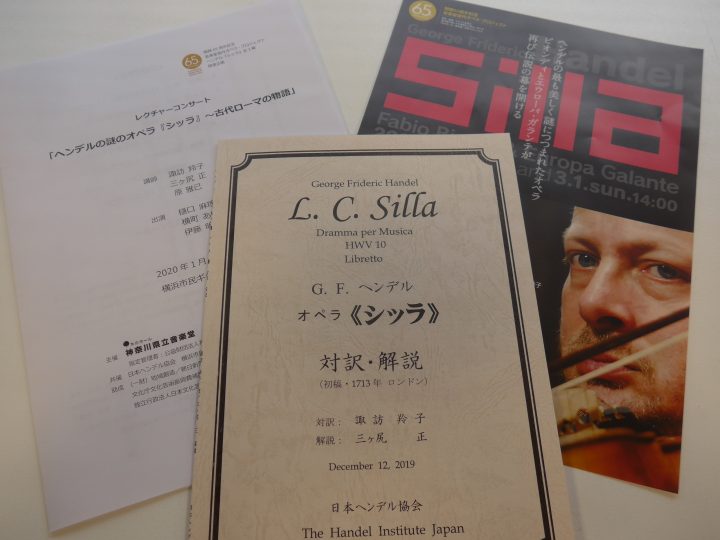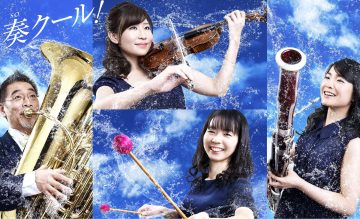クラシックとジャズの世界を往還する音楽家・小曽根真インタビュー 「音楽は言語と同じ」

Interview & Text:濱安 紹子 Photo:西野正将 201.3.8公開
「音楽は言語と同じ。たとえリズムや音が違ってもその根底にあるものは一緒」
日本が世界に誇るピアニスト/作曲家、小曽根真氏が取材の中で度々語った言葉だ。ソロ、デュオ、トリオ、バンドにオーケストラと様々な形態で演奏活動を行う傍ら、舞台や映像の世界をはじめ、多方面で作曲家としても手腕を発揮している同氏は、多様な言語を操りながら、心奥に潜む本質を捉えて表現するスペシャリストとも呼べるだろう。
近年ジャズの世界から飛び出し、クラシックの偉大なる音楽家、ショパンとモーツアルトの作品に挑んだ2010年発表の『Road to Chopin』、2015年発表の『Jeunehomme』からも窺えるように、現在はジャズとクラシック、双方の世界を往還しながらファンを魅了し続けている。この取材が敢行されたのは、同氏が<JAZZ JAPAN>誌の主催する「JAZZ JAPAN AWARD」の授賞式に向かう道中だった。坪口昌恭氏らとともに実行委員を努め、音大生のために立ち上げた「Jazzfestival at Conservatory」の活動が評価され、特別賞を受賞するに至ったのだ。その功績の数々を挙げれば枚挙に暇がないので、詳細は公式サイトのバイオグラフィに譲るとして、この記事ではそのルーツや変遷を辿りながら、クラシックとジャズ、そして音楽への向き合い方や表現者としての在り方を伺い、小曽根真という音楽家の人物像と興味深い音楽論を紐解いていきたい。
クラシックとピアノが嫌いだった幼少期
—近年クラシックの作品や公演に携わっていらっしゃる小曽根さんですが、実は5歳の頃にクラシックピアノを習い始めてすぐ、バイエルが嫌で辞めてしまったという経験をお持ちなのだとか。
最初に受けた30分間のレッスンでピアノが大嫌いになりました。バイエルって五線紙もおたまじゃくし(音符)もでかいんですよ。父親(小曽根実・ジャズピアニスト/ハモンドオルガン奏者)が音楽家じゃなければ、きっとそんなことには気づかなかったんでしょうけどね。いつも自宅で父の書く、細かくて綺麗なアートのグラフィックみたいなスコアを見てきたものだから、バイエルを見た瞬間、子供ながらにそれが“子供用に書かれた幼稚なもの”だっていうのが分かってしまって、何か馬鹿にされてるような気分になっちゃって(笑)。しかも、その頃から既に一本指で曲を弾いたりもしてたので、それを今更ド・レ・ド・レ……ってゆっくり鍵盤押さえて「よくできました!」って褒められてもね。もう、だんだん腹立ってくるわけですよ(笑)。で、「これが音楽かよ。ダサっ!」って思っちゃって。そんなわけで、ピアノ嫌い、楽譜嫌い、クラシック嫌いになってしまいました。
そんな経験もあったせいか、僕は常々「教育って何だろう」っていう疑問を持ち続けています。今ちょうど大学生たちと一緒にビックバンドをやっていて、今日参加する授賞式でも彼らと演奏をするんですけどね。日頃も学生と接する機会が多いので、教育についてはよく考えさせられます。

目指すのは“先生”にならない教師!?
— 今回は、その「Jazz Festival atConservatory」での功績が認められて、JAZZ JAPAN AWARDの特別賞を受賞されたんですよね。ここでは小曽根さんも教育者としての立場で関わっていらっしゃるわけですが、教育についてはどのようなお考えをお持ちですか?
ここで話すのはあくまで僕の考え方であって、色々な教育論があると思うんですが、教師が持っているものを生徒が取りにくるっていう形が、理想の教育なんじゃないかなと思ってます。一方的にものを教えるのではなくてね。そうなると、教師の役目って子供に興味を持たせることなんです。「あれしなさい。これしなさい」って言うのは簡単だけど、それだけじゃ応用が効かなくなってしまう。音楽を教えるというのは言葉を教えることと同じなんです。
— どういうことでしょうか?
例えば生徒は「でも」っていう言葉を使いたいのに、教師が「『しかし』って言いなさい」って言うとするでしょ。そうすると「なぜ?」っていう疑問が生まれる。その疑問がちゃんと腑に落ちない限り、「しかし」はいつまでたっても借り物の言葉なんですよね。音楽に関しては、そういう教育をしている人が多い気がします。僕の演奏を聴いて「私、昔クラシックピアノやってたんです。小曽根さんの演奏を聴いてたら、もっとピアノ続けとけば良かったなって思いました」って言ってくれる人が結構多いんです。で、その人がピアノを辞めてしまった原因を突き詰めていくと、やっぱり教師の教え方に問題があったんじゃないかなと。
—実はまさしく私も、幼い頃にピアノ辞めてしまったクチですね(笑)。
そうそう、実際多いんですよ。そして、自分が正しいことを証明するために教えている人も多い気がします。僕は自分が教える立場になった段階で、仕事に対する恐怖感が芽生えました。責任重大ですからね。今でも「“先生”にはならないようにしよう」と心がけています。常に現役の音楽家でありながら自分自身が成長していないと、学生に教えていくのは難しい。大学の教授になって週3回ほど学校に行ってると、自分の勉強する時間がなくなってしまうってことが現実問題あってね。これは学校というものを体制から立て直していかないと難しいんですよ。例えば教授も年に1ヶ月位は旅に出るとか、コンサートツアーを行うとか、そういったことをリクワイアメント(必要条件)として定められたらいいんですけどね。今の状況では実現が難しそうです。
クラシックと仲直りするまでの長い道のり
—お話を戻しますが、嫌いになってクラシックから離れてしまった小曽根さんが、再びクラシックと出会い、仲直りしたのはどんなきっかけだったんでしょうか?
(クラシックと関わる)チャンスは何段階かに渡って訪れました。はじめにクラシックを聴こうと思ったのはデビューの頃。ピアノ嫌いになった僕はハモンドオルガンをずっと弾いていたんですけど、12歳の頃にオスカー・ピーターソンの演奏を観て感動し、それからピアノを弾くようになりました。だけどジャズを弾きたかった当時の僕にとって、クラシックは単なる練習材料だったんです。テクニックを上達させるためのメソードに過ぎなかった。モーツアルトなんか弾いても何もピンとこなかったし。きっとバイエルをやった時の嫌な印象が残っていたんでしょうね(笑)。
—この段階では、まだクラシックに対する興味は湧かなかったわけですね。
ピーターソンみたいに弾くのが、当時の僕のゴールでしたからね。早く自分のスタイルを作らなきゃって、それを第一条件みたいに考えてたんです。でも今になって思うんだけど、20歳やそこらで自分のスタイルなんてできるわけがないんですよね。でも少なくともジャズ界においてはそれが求められていて、自分のコンポジションを描くことが必要だったんです。
案の定、当時の僕は何を弾いてもピーターソンみたいな音を出してしまっていて。このままでは良くないと悩み、再びクラシックの世界に興味を持ち出したんです。で、クラシックをやってる友人のピアニストに電話して、「クラシック聴いてみたいんだけど、何を聴けばいいと思う?」って相談しました。そしたら「小曽根くんはずっとジャズをやってきた人だから、ベートーヴェンとかバッハとか聴いてもピンとこないかもしれない。とりあえずプロコを聴いてみたら?」って言われて。そこで思わず「プロコって何?」って聞き返した僕に、「何じゃなくて人だよ、コンポーザーの人」って突っ込みが入りました。“プロコ”ってきっとジャンルの一部か何かだと思ったんですね。ほら、プログレとかそういう感じの(笑)。そのレベルだったんですよ、当時の僕の知識は。そんなこんなで、彼女に薦められたプロコフィエフのピアノコンチェルト3番を聴いてみたんですが、「クラシックの中にもこういうのがあるんだ!」って、見事にノックアウト!それをきっかけにクラシックを聴き始めました。

—そこからようやくクラシックに興味を持ち始めたと。実際にクラシックピアノを弾くようになったのは、その後のことなんですよね。
それから随分後のことでした。2003年に尾高忠明さん(指揮者・札幌交響楽団の名誉音楽監督でもある)が、札幌交響楽団の定期演奏会で僕にソリストをお願いしたいと仰られたのがきっかけです。……なんですけど、以前ラジオ番組で尾高さんが「小曽根くんといつか『ラブソティ・イン・ブルー』をやってみたい」って仰ってたのを聞いてた僕は、オファー頂いた時にきっと「ラブソティ・イン・ブルー」をやるもんだと思い込んでましてね。内容を確認せずに引き受けちゃったんです。で、その2〜3ヶ月後に当時の僕のマネージャーに「先方に連絡して何の曲がいいか確認して。多分『ラブソティ・イン・ブルー』だと思うけど」って電話で伝えたら、その2分後位に慌てて電話がかかってきて「あのう……なんか、モーツアルトって仰ってるんですけど」って。まさかそんな回答が返ってくると思ってもいなかったから、ビックリして「そんなはずないだろ!」って思わず口から出ちゃいました。で、一応「このタイミングじゃあ、もうキャンセルはできないよね」って確認したんですけど、「はい、もうキャンセルは無理です」って(笑)。しかも曲は僕に選んでほしいってリクエスト付き。ちゃんと聴いたことすらなかったもんだから、慌ててCD屋さんに行って7枚組くらいのモーツアルトのコンチェルト全集を買いましたよ。いまだにそのCDは自宅にあると思います。で、10日間位かけて全曲聴いて、その中から9番の「Jeunehomme」を演奏曲に選びました。
—かなり切羽詰まった状況でクラシックピアノを始めることになったんですね(笑)
演奏した日はものすごく緊張しました。何弾いたかも覚えてないし、身体が硬直したせいで腰痛めちゃって。普段は割とリラックスして弾く方なんですけど、あの時は演奏終わって「腰痛っ!」って思ったことくらいしか覚えてない(笑)。演奏自体は事故もなく無事に終えたんですけど、後から録音した音源を聴いたら、やっぱり全然思うように弾けてなくてがっかり。尾高さんは素晴らしかったって言ってくれたし、色々な人に僕の演奏が良かったと広めてくださったんですけどね。でも、それをきっかけに色々なオーケストラから「うちでもモーツアルトやって」とお声かけ頂くようになりました。また、そのご縁で今の事務所の方から、「Jeunehomme」をラ・フォル・ジュルネでやってほしいと依頼をもらい、2006年に公演が実現したんです。
小曽根流・クラシックとの付き合い方
—その思い出深い曲が、昨年出された同名のアルバム『Jeunehomme』の題材となったわけですね。
アレンジをするには曲を熟知していないといけませんからね。僕がまずやるとしたらやっぱり「Jeunehomme」だろうって思って。と、いいつつ完成までに3年かかりました。構想練るのに2年10ヶ月、残り2ヶ月で曲を書いて。あの時はずっとお風呂で曲考えてましたね。僕、お風呂に浸かりながらよく曲考えるんですよ。「イントロをこうして、ああして……」って感じでね。
—意外な場所で曲が生まれていたんですね。クラシックに関しては独学で学ばれたんでしょうか?
一度ちゃんとクラシックを勉強しようと思って、1学期間だけクラシックの学校にも通いました。2004年だったかな。イーストマン音楽院(アメリカの音楽学校)に友人のピアニストがいたので、お願いして色々教えてもらったんです。コンダクティングやオーケストレーションとか、あとやったことのない対位法(作曲法)とかね。とにかくこの4ヶ月だけは絶対ジャズを弾かない、と決めて取り組みました。その辺りからクラシックにどっぷりとハマっていきましたね。
— 『Road toChopin』と『Jeunehomme』の2作品においては大胆なアレンジが施されていますが、その中で『Road to Chopin』の「エチュード」は唯一、譜面通りに弾かれた曲だと伺っています。その理由を教えてください。
クラシックの音楽家たちに対するリスペクトの表れです。あとは、クラシックファンに向けての名刺代わりというか。せっかくショパンの名前を使わせてもらって作品を作るんだから、せめて1曲くらいはボロボロでも頑張って譜面通りに弾くんで、どうぞ宜しくお願いしますってね。ジャズの人間がクラシックの題材だけ使って全部自分流に料理するより、そっちの方がいいかなと思ったんです。日本料理といいながら、全部材料をごま油で炒めて中華風の味付けにして「はい、どーぞ」じゃ、和食家に対して失礼じゃないですか。だから「ヘタクソだけど一生懸命、基本の煮物を作ってみました」みたいな(笑)、そういう気持ちで弾いたんです。
—なるほど、料理に例えると分かりやすいです(笑)。
クラシックとジャズの違い=自由と葛藤の種類
— クラシックとジャズで演奏する時の違いはありますか?以前他誌で受けていらしたインタビュー記事の中で、ジャズと比べてクラシックは「すごく深い部分に無限の自由がある」と語られていたんですが、どういうことなんでしょうか?
ジャズは即興がメインですけど、即興で演奏する音楽の限界、というかデメリットみたいなものにも気づいてしまって。使える言葉って自分の持っているボキャブラリーの中からしか出てこないんですよね。そうすると、自分で自分のボキャリーを作り続けなきゃいけないっていう葛藤もあって。一方でクラシックという音楽の場合は、常に自分というか、自分の業と向き合わされるんです。自分がどう感じるか、どう弾きたいかってことを含めてね。例えるならジャズは日常会話、クラシックの場合は台本がある芝居。それをどう読み解いていくか、というところに面白さがあります。弾けば弾くほど疑問も出てきますけどね。クラシックの場合、ジャズと違って弾く音は大体決まってるんですが、その時その瞬間に生まれた気持ちにどれだけ忠実でいられるか、ってところがジャズと同じ気がしていますし、それがきっとクラシックへの僕の向き合い方なんですね。今は弾いているとすごく気持ちが自由になります。
—ジャズとクラシックでは向き合い方の種類が異なると。
ジャズを即興でやる場合は、常に怖い所にいかなきゃダメなんです。でもクラシックの場合は、題材を掘り下げていくっていう向き合い方をしないといけない。まあ、あんまり考えすぎちゃうとヘッディーな音楽になってしまうから、あくまでも自分が意図したことを弾いてそれが自分の心に響いてくれること、それを目標にしています。ここ(胸を指しながら)に響いてないものはお客さんに伝えられないんです。だからお客さんに「どうですか、コレ?」って尋ねながら弾くのって、僕は失礼にあたるんじゃないかなって思うんです。やっぱり自分が「コレだよ、コレ!」って思うものを弾かないと。
—音楽以外にも通ずる、プロとしてすごく大切な意識のあり方ですね。大変勉強になります。だからこそお客さんの心に響かせられるんですね。
心に響かせるということ
自分が何かをできるということを証明するために音楽やっている人が、ジャズもクラシックも多い気がするんです。僕は時々そういう人たちを見て「ウッ」ってなっちゃう。これは僕の好き嫌いだから、そういう人やそういうのが好きなお客さんがいてもいいとは思うんだけど、やっぱり聴いた瞬間にジンとくる音楽ってあるでしょ。例えば「あなたのことが好きです」って言うとして、タドタドしいけど何とかその人なりの気持ちを伝えようとする人と、ものすごく流暢なんだけどなんか言い慣れてる感じの人がいるとするじゃないですか。後者が「僕はすごいんだ!だから僕といると幸せだろう」って感じのやつだったら僕は、その辺にあるモノ投げたろか! みたいな気持ちになっちゃう(笑)。それって音楽でも一緒なんです。
それがどんなに高尚な音楽であっても関係なくて、結局は聴き手が生理的にどう感じるかってことが大事。これに関しては嘘つくことができませんからね。例えばアルゲリッチが、「こんなのベートーヴェンじゃない」って感じの弾き方をしたっていいんです。おそらく彼女の中では彼女なりのベートーヴェンができあがってるんだろうし、僕からしたら当のベートーヴェンがどんな弾き方してようが関係ない。あの30分のコンチェルトの世界にぐわーっと連れていかれて、終わった瞬間に立ち上がって拍手したくなるような高揚感と幸せを頂く……これこそが「This is Music」。そしてそう考える時、ジャズもクラシックも全部同じな音楽なわけです。

音楽は言語。大切なのはその根底にある普遍的なのもの
いわゆるクラシックポリスと呼ばれる人たち、あ、ちなみにジャズポリスってのもいますけどね。彼らの中には「あれはモーツアルトじゃない」とか、言ってくる人もいるんですよ。まあ、でもプロコフィエフくらいまでいくと誰もあんまり文句いわなくなるっていう不思議もあって。だったらモーツアルトにも文句いう筋合いないやん、と突っ込みたくもなるけど(笑)。そんなに自分が知ってる演奏を聴きたければCD聴くしかないでしょ。これはお芝居や映画のリメイクに関しても同じことで、例えば「あれはシェイクスピアじゃない」なんて評価のされ方もありますよね。だけど、シェイクスピアが本当に伝えたかったことを理解した上で現代版に置き換えるんだったら、どんな形であれ、すごく素敵なことじゃないですか。
音楽でいえば、難しくて複雑な音を出していても、たとえ不協和音を出していたとしてもいいんですけど、出てきた音そのものが自分に対してどういう化学反応を起こすのかってことを生理的に理解していないと、音楽を奏でる上であまり意味がない気がします。そして、そういうところで音楽と向き合うと、ジャズもクラシックもロックもポップスも全てのジャンルが関係なくなるんですよね。音楽は言語と同じ。ジャズが英語だとしたらクラシックはドイツ語、リズムと音が違うだけで結局、根底にある伝えたいことは一緒なんです。つまりどんなジャンルであれ、違うのは言語だけってことになります。
—小曽根さん自身、これまでコラボレーションされた方々の名前や発表された作品を見てわかるように、ジャンルを超えた様々な音楽を手掛けてきていますよね。最後に、そんな小曽根さんの今後の展望について教えてください。
まず、3月20日に神奈川県立音楽堂で コンサート (サックス奏者である近藤和彦氏と共演)を行い、その後5月から チック・コリアとデュオで行うツアーが始まります。クラシックに関しては海外公演もやっていきますし、秋以降にウィーン・トーンキュンストラー管弦楽団やベルン交響楽団と、さらに来年には引き続きニューヨーク・フィルハーモニックとも一緒にやります。それにソロコンサートも続けていく予定です。ソロって自分が一番裸にされるものだし、己と向き合わされるんですよね。毎回成長する姿を見せられるようになりたいし、真剣勝負でこれからも挑んでいます。来年にはトリオも復活させたいと思っているし、色々なプロジェクトとやりたいことがいっぱいです。
— 今後のご活躍を楽しみにしています!本日はどうもありがとうございました。
短い時間だったが、生演奏を目の前で体験しているような濃厚でエキサイティングなインタビューだった。その後、小曽根氏の後を追ってその場を後にし、JAZZ JAPAN AWARDの会場へと移動した私は、同氏が指揮を執る「Jazz festival at Conservatory」の演奏を聴いた。はじめはステージに上がる初々しい音大生たちの面持ちを微笑ましく見ていたのだが、演奏が始まってからは、想像していたビックバンド像とは全く違う感触の、規格外なパフォーマンスに吹っ飛ばされてしまった。……ここでライブレポートをすると長くなってしまうのでやめておくが、とにかく生で感じて頂くのが最良だ。その音楽と空間を味わえば、きっと同氏の語った言葉の意味を肌で感じ取ることができるだろう。クラシックやジャズをよく知らなくても大丈夫。言葉の通じない外国人と接した経験のある誰もが「言葉が分からなくても、案外何とか気持ちは通じるもんだ」と感じるように、ジャンルなんか分からなくても音楽は十分に楽しめるものなのだと、改めて感動するだろう。——音楽と言語の共通点は確かに多そうだ。ひょっとして、今日こんなにも多くの種類の音楽が存在しているのは、大昔バベルの塔が崩壊して世界中の言語がバラバラになってしまったおかげなのかも……、取材を終えてふとそんなことを思った。
▽小曽根真さんの今後のご活動の詳細を知りたい方はこちらから
▽小曽根真さんが出演する神奈川県立音楽堂でのピアノコンサート情報は下記関連イベントをご覧下さい。