田中千智インタビュー|「絵描きは孤独じゃない」という発見

Interview&Text :内田伸一 Photo (Portrait) :西野正将
収録協力:ビストロバーガー 下北沢グリル
横浜市民ギャラリーの「ニューアート展NEXT」は、創造都市横浜からの発信をテーマに、横浜と関わりのある気鋭の若手作家を紹介する毎秋の注目企画。その3 回目に登場するのが、画家の田中千智さんだ。近年は地元の福岡県でも「福岡アジア美術トリエンナーレ2014」に参加するなど活躍中の彼女は、2008年、第一回の「黄金町バザール」で100人以上の地域住民の肖像画づくりに挑戦した。それは画家として活動する上での大切な気付きをもたらすことにもなったという。それから7 年を経て開催する今回の展覧会は、横浜との久しぶりの再会であると同時に、ギャラリーと街中での展示で約86点もの作品が集う、過去最大規模の個展。現時点の彼女の集大成にして、新たな創作のスタートラインにもなるものと言えそうだ。開催直前のある日、シンプルに「絵描 田中千智」とだけ記された名刺を受け取ることからインタビューは始まった。
「107人のポートレート」制作秘話

田中千智「107人のポートレート」展示風景/2008年/黄金町バザール(神奈川)
──今回の個展で展示される作品群のうち、「107人のポートレート」は田中さんと横浜の最初のつながりとなるものですね。2008 年、第一回の「黄金町バザール」における滞在制作で生まれた、肖像画シリーズです。
田中:はい。黄金町で飲食店を営む皆さんを中心に肖像画を描かせてもらい、それぞれのお店で展示してもらうプロジェクトです。観客にとっては、それを見に行くことで黄金町駅、日ノ出町駅を周遊できるというものでした。
──それが地元の方々と来場者、双方にとってアートを通じた町との架け橋になる、という試みでしたね。このアイデアはどこから生まれたのでしょう?
田中:ディレクターの山野真悟さんからの提案でした。私と山野さんは同じ福岡県出身ということもあり、それまでも地元で折にふれてお話する機会があったのです。
──では、そんな交流も元に、田中さんの創作スタイルを活かした提案だった?
田中:それが私、そのときまで実在の人物をモデルに肖像画を描いたことはなかったんです(苦笑)。なので正直に言うと、最初は「えぇ〜、私がそんなことを!?」という困惑もありました。ただ、逆に考えると、こうした機会だからこそできる自分にとっての挑戦でもあるのだろうと思えてきて。それで、とにかくやってみようと決めました。
──実際には、どんな流れで107人もの人々を描いていったのでしょう?
田中:まず対象地域の飲食店に一軒ずつ連絡をとり、私と事務局の担当者さんで直接伺うなどしてプロジェクトの主旨を説明し、賛同を頂けた方々を描かせてもらいました。でも、突然よそからやってきた画家がそんなお願いをするわけなので、やっぱり色々難しさはありました。「それで、これはお金とられるの?」と聞かれたり(苦笑)。
──確かに、油絵で自分の肖像画を描いてもらう機会というのは滅多にないですし、ちょっと警戒するのも自然な反応でしょうね。加えて「黄金町バザール」の最初の開催でしたから、まだどんなことが起こるのか誰も想像しにくかったのでは。
田中:ただ、こちらの意図をわかってもらうために説明を一生懸命するなかで、自然と相手の方ともいろいろお話させてもらえるんですよね。いわゆる聞き取り調査のようなものではなく、自分たちの町を今後どうしていきたいのか、というようなことも含めて。

──黄金町バザールが誕生した背景には、かつて多くの違法飲食店もあった地域を、新しいかたちで町の活力や交流が生まれる場にしよう、という願いがありました。
田中:はい。みなさんそこについては、やっぱり自分たちの町をより良い所にしたいという強い気持ちを抱いているようでした。ただ、そのためにどうすべきか、という具体的なところでは、意見もさまざまだったと感じます。「でも、アートで何が変わるの?」という意見も実際に投げかけられて、私はそれに対して明確に答えることはできませんでしたが……。
──でもそこでは、田中さんが行政関係者でもルポライターでもなく、またリサーチを得意とするようなアーティストでもなく、「ただ肖像画を描かせてもらいたい」というシンプルな立場で訪れたからこそ、交わし合えた言葉もあったのではと推測します。山野さんの意外な提案も、そこに真意があった?
田中:そうだったのですかね(笑)。ともあれ約2ヶ月のあいだ、市内に用意された作家滞在施設で暮らしながら、みなさんを訪ね、写真を撮らせてもらい、ひたすら肖像画を描くという日々を過ごしました。飲食店の方々以外にも、役所関係の方や、黄金町バザールの事務局スタッフなど、色々な方を描かせてもらって……。結果として、ひとつの地域に関わる様々な人に出会い、彼らを描くという体験は、私にとってもすごく貴重な日々になりました。また、同じく滞在制作で訪れていた作家さんたちと交流できたのも、良い体験になりました。
──モデルとなってくれた個々の方々との思い出はありますか?
田中:描かせてくれるとなると、一人ひとり、様々なリクエストも出てくるんですよね。孫や愛犬など大切な家族と一緒に描いてほしいとか。また、お店の切り盛りで忙しい方々が多いので、制作用にはまず写真を撮らせてもらうのですが「それなら日を改めてまた来てちょうだい!」と言われたり(笑)。
──やっぱり肖像を描いてもらうとなると、身繕いも気になりますからね。度々訪ねるのは大変そうですが、対話を重ねることにもつながりそうです。そうしたやりとりも、個々の人生や暮らしの気配として肖像画に反映されたのではないでしょうか。
田中:完成した肖像画は、お礼の意味も込めて、展示後にご本人たちに差し上げることになりました。今回、7年ぶりにそれらをお借りして展示しようとギャラリー側から提案されたとき、心のどこかで「もう残っていないのでは……」という不安がありました。でもみなさん取っておいてくれたようで、嬉しくてちょっと泣きそうになりました。今回もギャラリー展示に加え、会期中、各店舗に飾って頂くところもあります。
──モデルになってくれた方のお一人が、2008年のプロジェクト後に田中さんの別の作品を購入してくれた、というエピソードもあったとか。
田中:はい。サイレントオークションという形式で、絵を購入したい方々がそれぞれ希望の値段を書いて箱に入れる、という競売の催しがあったのですが、一番の高値をつけてくれた方のお名前を見たら、「あ、あのお店の人だ」ということがあって。
──画家とモデルの関係から、コレクターが生まれたわけですね。
田中:すごく驚いたし、「ひとこと言ってくれたらいいのに!」と思いましたけど(笑)、それは本当に嬉しかったです。今回、その方にコレクションしていただいている作品の中から一つ作品をお借りして、出展できることになりました。
「背景」を想像させる漆黒の幻想画
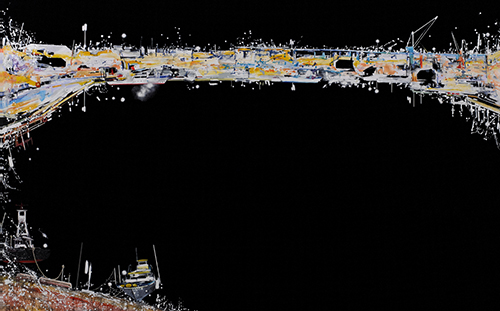
《きょう、世界のどこか》/2011年/油彩、アクリル、キャンバス/227.0×364.0cm
──今お話に挙がった作品もそうですが、「107 人のポートレート」とも大きく異なる作風の絵画群がありますね。背景は白が基調だった「107 人のポートレート」に対して、こちらは漆黒の背景に、幻想的できらめくような人物や都市の姿が浮かび上がるものです。近年の田中さんの代表的な創作スタイルといっていいでしょうか。
田中:じつはこうした絵を描き始めたのも、ちょうど黄金町の滞在制作が決まった時期と重なっています。それまで絵を描く上で、背景をどうするかが悩みの種でした。これだというものがなかなか決められなくて。そこで、いっそ背景は何もない状態にしてしまったらどうだろう? というのがきっかけです。
──吸い込まれそうな黒が背景になることで、描かれる者たちの謎めいた雰囲気も引き立ち、そこにある豊かな物語を想像させるような印象です。
田中:最初は背景も油絵具で塗っていましたが、独特の艶があるので暗闇が変に主張してしまうように感じました。それで背景のみアクリル絵の具を使ったところ、フラットな黒が表現できて、前景との対比やよい意味での違和感も出せるように感じ、この組み合わせを選んでいます。
──これらにおいては、描かれるモチーフのモデルがいるのですか?
田中:いえ、いつもだいたい、黒い画面の真ん中に何か描いてみて、これは人かな、女性かなといった感じで、ゼロから始めて描きながら発想していく感じです。そういう意味でも「107 人のポートレート」とは異なる描き方だと思っています。
──ふたつの対照的な創作を、ほぼ同じ時期に試行錯誤したわけですね。
田中:そうですね。もうひとつ、黄金町での体験を基に変わったことを挙げるとするなら、その後は書籍の装画や音楽アルバムのジャケット、映画祭や演劇公演のポスタービジュアルなどのために絵を描く機会も増えたということです。たまたまそういう依頼を頂き始めた時期なのもありますが、今思うと、黄金町でのプロジェクトで気付いたことが影響しているかもしれません。

《天使エスメラルダ》/2013年/油彩、アクリル、キャンバス /80.3×130.3cm
──気付きというのはどんなものでしょう?
田中:それまで、絵はひとりで描くものだ、ある意味では孤独な創作だという考え方でいた自分が、人と関わりながら描くこともできるんだと思えたんですね。また、肖像画というのは、自分に似ているということがモデルの方々にとっては一番嬉しいことなのだなと実感しましたが、誰かの気持ちに応える絵、というのもやってみていいんじゃないか、と考えるようになって。もちろんこれまで通り、誰に頼まれるでもなく描くことは続けながら、ですけど。
──そのことが、また自身の中で発見につながることも?
田中:たとえばここ数年、北欧映画をテーマにした映画祭「トーキョーノーザンライツフェスティバル」のメインビジュアルを担当しています。依頼のきっかけが、黒を背景にした私の絵画群が「北欧っぽい」ということだったようで。じつは私、北欧には一度も行ったことがないんですけれど……。それで改めて考えてみると、あの黒はむしろ、自分が子ども時代を過ごした故郷の糸島市——当時はすごく田舎で、夜になると街灯もないので月明かりだけで照らされる風景——と関係があったのかな、と思ったり。また、依頼されて描く際には「どういう内容だと喜んでもらえるかな?」と考えるわけですが、それがこれまでの制作とはまた違う刺激になることもありました。

演劇「血の家」チラシ/「トーキョーノーザンライツフェスティバル2015」チラシ
ひとりの絵描きが彩る多面体
──ここまでお話を伺ってきて、今回の個展はそんな田中さんの現時点での集大成というか、さまざまな生まれた方をした絵画が一堂に会する機会でもありそうですね。
田中:そうなんです。今回は、まず会場の一階で「107 人のポートレート」と、依頼を頂いて生まれた作品群を展示します。本やCD、映画祭などを通じて私の絵を知ってくれた方々も含め、展覧会への間口はできるだけ広くして来場者を迎えたいと考えました。続く地下の展示空間では、絵描きとして自ら制作してきた作品群を展示します。これは今回のための新作に加え、幅3mの大きな絵画や、福岡アジア美術館などで発表してきた作品、また福岡と韓国の釜山で表現者たちが交流する「WATAGATA info 福岡プサンアートネットワーク」などへの参加を通じて生まれたものを含みます。
──横浜、福岡、釜山……いずれも様々な文化が行き交ってきた港町なのも、何だか興味深いです。色々な見えない「つながり」も現れてきそう?
田中:そう言われるとそうですね(笑)。つながりと言えば、会期中にはピアニストの林正樹さんによる、展示空間で一夜限りのライブも予定しています。彼とベーシストの西嶋徹さんによるアルバムのジャケットを描かせてもらった縁で、今回実現できることになりました。ですから、どこかで私の絵を知ってくれた人も、同じ画家が手がけ、関わってきた色々な面にふれて頂けたら、という想いがあります。もちろん、黄金町で肖像画を描かせてもらった方々に向けても同じ気持ちがあります。こういうこともやってきましたって。あのときの肖像画のイメージが強いと「なんだか暗い絵だな?」なんて言われるかも、と心配しつつ(笑)。
──そこで先ほど話に出た、コレクターになった方が登場して「ほらほら、ここが魅力的でしょ!?」と解説が始まったりしたら、楽しそうです(笑)。最後に、個展タイトルについて教えてください。「I am a Painter」(私は絵描き)というこの言葉は、シンプルながらとても強い言葉ですね。ご自身で決めたタイトルですか?
田中:はい。ある時期から、自分が「アーティスト」や「現代美術家」なのかどうか、モヤモヤ考え続けていました。美大時代は具象画、抽象画に加えて現代美術のコースにも参加したのですが、自分は複雑なコンセプトによる創作よりも、とにかく絵を描くことが一番しっくりくるようだ、と自覚しました。そこから今日お話してきたような出来事も経て、最近は日々の暮らしに「絵を描くこと」を自然に組み込めたらと思えるようになりました。だからここで一度、シンプルに振り切って「絵描き」とだけ名乗って自分の絵画を見てもらおう、それをひとつの区切りとして、また描き続けていけたら——今はそんな想いでいます。ぜひ、多くの方々が会場を訪れてくれたら嬉しいです。
CHISATO TANAKA/[I am a painter ] from 田中千智 on Vimeo.



