あざみ野フォト・アニュアル『考えたときには、もう目の前にはない』| 石川竜一インタビュー

2016.2.14公開 Interview&Text:渡邊浩行 Photo(Portrait):西野正将
石川竜一という写真家を知ったのは確か2014年の11月。「友達の面白い写真家が渋谷で展示をやっているから見に行って」と、沖縄で知り合った女友達から知らされた。のちに木村伊兵衛写真賞受賞作となる『okinawan portraits 2010-2012』が刷り上がる直前のタイミングで、会場で会った石川さんはしたたかに酔っぱらっていたから、後日、銀座ニコンサロンでの個展にお邪魔して、あらためて話を伺った。大きなリュックサックを背負い、デジタルバック付きハッセルブラッド2台を首からぶら下げて銀座の路地からふらりと現れた石川さんは、沖縄出身者らしく、ゆっくり、ていねいに、1つ1つ言葉を選びながら質問に答えてくれた。誠実な人だと思った。あれから1年。個展「考えたときには、もう目の前にはない」の準備で忙しいなか、久しぶりに会った石川さんは相変わらず控えめで、誠実で、優しく濡れた眼をした、イカした(イカれた?)沖縄の“にーにー“ だ。
写真展はその時々の「点」を打つことに過ぎないから、いままで撮ったものをとにかく出す
「考えたときには、もう目の前にはない」では、石川さんが写真家として認められる以前の初期の作品群に、木村伊兵衛写真賞受賞作である『絶景のポリフォニー』と『okinawan portraits 2010-2012』。加えて、最新作の『CAMP』が初お目見えする。石川竜一という写真家と作品世界を知るには格好の構成だと思う、そう伝えると、「死んでもないのに回顧展みたい」と苦笑していた石川さんだが、展示の意図はシンプルだ。
「いま出せるものを全て出すだけ。人って頭の中でいろいろなことを同時に考えていますよね。展示したポートレートもスナップも、ポラロイド写真も同時並行で撮影しているし、初期の作品は写真に対して試行錯誤していた時期のものではあるけれど、それはいまでも変わらないんですよ。写真に答えなんかないし、でも、それを考えることだけが自分には必要だと思っていて。展示の構成の意味とかをいま考える必要はないと思うんですよね。人が考えてきたことは、結局はその人が死ぬ時までわからなくて、どこかで何かが完結しているわけではないから。あえて言うなら、『いま自分はこう思っている、ここではこう思った』っていうポイントを打つ感じ。その時々に、できるだけ正直に、可能な限り向き合うなかから生まれたものを瞬発力で発表する。そういう風に何か残していけたらいいと思っています」

自分一人の想像力は小さ過ぎて、世界が魅せるポリフォニックな有り様の足元にも及ばない
出展作品のなかで『ryu-graph』は異色だ。印画紙に直接溶剤を塗ることで制作されたこの作品には、いわゆる写真とは違った、石川さんの内側にあるイメージが直接的に表現されている。制作していた時期、石川さんはほとんど人に合わず、写真も撮らずに家に引きこもった状態だったいう。きっかけは、写真に対する意外な気づきからだった。
「写真を始めた最初の頃は、目に入った気になるものをスナップしていました。でも、プリントしたら撮った時のイメージとは全然違っていた。それで、『写真って何も写らない』って思ったんですよね。考えてみれば、人は何かを目の当たりにした時、たとえば朝何を食べたとかその日の天気、空気の感じ、嗅いだ匂いとかを全部踏まえたうえで初めて何かを感じるわけですよね。そこまでの経験が違うから、同じものを見て同じことを感じるわけじゃないんですよ。それで、いろいろなイメージを組み合わせれば、自分の想っていることを伝えられるんじゃないかと思って合成写真(『脳みそポートレイト』)を始めたんです。そこからは、決まりを設けずに、自分が考えていることを一度めちゃくちゃにして、やりたい放題にやったらどうなるかに興味が出てきて、多重露光やコラージュ、フィルムを焼いたり、現像液ほか薬品を使う手順を変えたりと、あらゆる方法を試しました。そうこうするうちに写真を撮ることさえしなくなった」

画像左:Ψυχή(animaプシュケー)/2007年/ゼラチンシルバー・プリント
画像右:ryu-graph #0028/2009年/ゼラチンシルバー・プリント
「撮る」から「伝える」というプロセスで生じる、見る側と見せる側とのコミュニケーションギャップをコントロールできないことの歯がゆさが、自身の内にあるイメージをそのまま表現しやすい合成写真、さらには『ryu-graph』へと石川さんを向かわせた。写真家でありながらカメラを使わずに制作を続けるなかで、なにか発見はあったのだろうか?
「人一人の想像力がいかに小さなものかということです。『俺ってこんなもんか』って。もっと面白いことができると思っていたけれど、大したことがないってわかった。さらに発展させるためのアイデアや方法、具体的なイメージはあったけど、くだらないと思いました。先が想像できる段階で終わってるんじゃないかって」
『ryu-graph』をやりきった石川さんは暗室を出て、手始めに身近な人や場所、そこで起こる出来事をスナップし始める。それがのちに『adrenamix』へと結実する。限りのある自分の内面から予測不可能な外の世界へ、という石川さんの意識の転換を端的に表しているのが、同じ時期に作られた『印画鏡』だ。
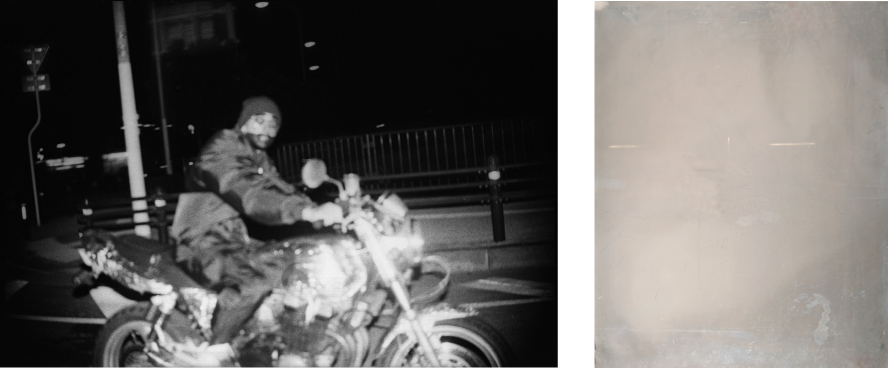
画像左:浦添, 2009(adrenamix より)/2010年/PC、モニター
画像右:印画鏡02/2010年/ゼラチンシルバー・プリント
「外の世界にある何かをもう一度、印画紙に写し込みたいと思って」
銀塩写真では、印画紙に塗布された銀に光を当てることで起こる化学変化を利用して、イメージを現像し定着させる。現像工程における銀の化学反応を応用してモノクロ印画紙を鏡面に作り上げたのが『印画鏡』だ。鏡は外側にある何もかもを写し出す。像は一瞬ごとに移り変わり、次の瞬間に何が写るのか予測がつかない。
銀座で初めて話を聞いた時に、この男は世界のあらゆるものを写し取る “巨大なイメージセンサー”になろうとしているのかもしれない、と感じたことを鮮明に覚えている。「なんでも写真になればいいのに」と折に触れて口にする石川さんの強い想いが『印画鏡』から感じ取れる。
時代とか場所は関係なしに被写体の放つ『摩擦』の力に震えてシャッターを押す
『絶景のポリフォニー』と『okinawan portraits 2010-2012 』に見る石川さんの写真の特徴は、一言で言えばその “鮮烈な生々しさ” だ。

八重瀬, 2014(絶景のポリフォニーより)/2014年/インクジェット・プリント
南国の熱く湿った空気の中で腐りかけた果実から漂う濃厚な臭気を思い起こさせる、ヘビーなイメージのたたみかけるような連射。「写真にはそこにあるものしか写らない」というのは一抹の真実だけれど、確実に何物かがそこにいることを感じさせる。石川さんは何を見て、どんなときにシャッターを押すのだろう?
「自分が何を見ているのかあまり深く考えることはないんですが、写真展やイベントのさいに『どんな時に写真を撮るのか』について訪ねられたことがあって、そのとき、『『生きてる!』って思った時とか、『ヤバい!』って感じた時に撮る』って答えていたんですね。そこから最新作の『CAMP』に繋がるのですが、そもそも森に興味はなくて、自分の想像を超えたことだからやってみたい、っていう気持ちで話に乗ってはみたものの、森に入ったら何を撮ればいいのかわからなかった。でも、何か撮らないと始まらないから撮る。現像して、プリントして、見返してという繰り返しの後で最終的に選んだものって、『絶景のポリフォニー』や『okinawan portraits 2010-2012』の時の言葉で言えば、『生きてる!』っていう感じのイメージだったんですよ。あえていま言葉にするならば、何かが動くときの『摩擦』の力というか。動物と動物がそこにいることから生じる摩擦とか、水が流れて岩を削る時の摩擦。それが面白いって。摩擦の力が大きければ大きいほど震える感じなんです。街には人と人がすれ違うときの物理的な摩擦もあれば心情的、感情的な摩擦もある。生きているなかで起こる事件や経験のようなものは、そのままその人に生じた摩擦を表しているのかもしれない。生きてるってことはそういうこと。摩擦の集積なのかなって思うんです」
石川さんの撮る人たちには、一見奇抜な風貌の人もいるし普通の人もいる。ただ、共通して言えることは、どのモデルもその人の「個」のようなものが際立っていることだ。

OP.001143 那覇(okinawa portraits 2010-2012より)/2013年/インクジェット・プリント
「ポートレートについて言えば、つまるところは個人を見ていることになります。でも、本当は個人も見ていないのかもしれない。撮影時にはわからないことのほうがほとんどなんです。ただ、これは反省点でもあるんですが、特異なものを見ようと偏るところはある。本当は、時間があればあるほどありがたい。外見に惑わされることがなくなりますから。時間さえあればわかりやすいほう、楽なほうに行こうとしない。危ないことだなって思います」
ある雑誌のインタビューで、写真家の藤原新也さんが「いまは個人ではなく群れが顔となる時代だと思う」と語っていた。2001年のアメリカ同時多発テロから2011年の東日本大震災と、それにともない発生した原発事故以降は「5分後にはとつぜん何が起こるかわからない時代」であり、群成することで人は安心を担保しようとする。それを象徴するのが、AKB48に代表されるグループアイドルの人気であり、彼女たちが巻き起こす現象そのものが、先の見えぬ不安を抱える現代の若者たちのシェルターとして機能している、というのが藤原さんの見立てだ。
なるほど確かに、AKB48やEXILEがJ-POPチャートの上位を独占し、街を歩けばクローンのような身なりの若者たちと大勢すれ違う。その姿に「個」のようなものを見出すのは難しい。
しかし、図らずも、藤原さんの言う「群れが顔になる時代」の只中で写真という表現手段に出会い、撮影を続けてきた石川さんのポートレートには、AKB48もEXILEもいない。それぞれの存在感が際立ち、その人にしかない体臭のようなものを烈しく発している。石川さんの言う「摩擦」の集積が「個人の顔」を作るのだとすれば、選ばれたモデルたちは、自覚の有無は別として、良くも悪くもその人自身の人生を生きてきてしまった人たちなのだろう。石川さんは彼ら彼女らの積み重ねてきた摩擦が発するヴァイブスに感応し、シャッターを切る。時代の影で見えにくくなった、本来は唯一無二であり多様であっていいはずの人間の有り様、実存のようなものが放つ一瞬の反射に、見る者は刺され、鮮烈な生々しさを感じるんだ。

OP.002187 那覇(okinawa portraits 2010-2012より)/2012年/インクジェット・プリント
写真は時代性や土地性のようなものが否応なく写し込まれるメディアだ。自身の写真と時代や場所との関わりについて、石川さんはどう捉えているのだろうか?
「時代や場所がどういう状況かといったことは写した写真を見て考えることで、先に考えてしまうことは自分にとっては意味がない。そういった要素を前もってイメージしてしまうことが既にアウトなのかもしれません」
撮影時にあらかじめ時代や場所を意識することは、『ryu-graph』で突き当たった、器の知れた己の想像力と同様に、石川さんが世界を捉える眼差しを曇らすノイズであり、写真を撮ることの足枷でしかないのかもしれない。
生きることは常にギリギリで、安定が一瞬のことでしかないのは街場の人間も同じ
『CAMP』は、サバイバル登山家の服部文祥さんと、撮影機材と命をつなぐための最小限の装備だけを持って人気ない山林に入り、撮影されたシリーズだ。昨年6月には石川県を流れる犀川の源流域に、9月には秋田県の和賀山塊で撮影は行われた。

画像左:C.09(CAMPより)/2015年/インクジェット・プリント
画像右:C.43(CAMPより)/2015年/インクジェット・プリント
主に沖縄の人と街を撮り続けてきた石川さんにとって、原生林のように人の痕跡すら見られない場所での撮影は初めての試みとなる。いつもとは真逆の撮影環境に身を置いた石川さんは、どんな感情を抱いたのだろう?
「普段とは全く違うものを見せられて戸惑いました。何を撮ればいいのかわからないんです。道もないし、人もいないし、ハンバーガー屋もない。毎日見ているものが何もないから、何をどう見ればいいのかさえわからない。だから、とにかくシャッターを押すしかありませんでした。写真を撮っているという実感は全くなくて、撮る理由もわからなくなった」
撮影中、記憶に最も強く焼きついているシーンは、犀川の雪渓を渡っていて足元が崩れ、死にかけた時のことだそうだ。
「『小さな雪渓だから、1人ずつ歩かないと崩れて2人とも終わる』と服部さんに言われて、先を歩く服部さんの見えない背中を追うように歩き出したときに、足元の雪渓が崩れ始めたんです。落ちたら死にますから、まるでマンガみたいに崩れる雪渓の上を必死で走りました。でも、ここで何か撮らなきゃ、この怖さ、気持ちを形にしないと、と思って振り返り、とにかくシャッターを押したんです。画像をチェックしたら、カメラの故障できちんとは写っていなかった。そのバグを起こした画像とその時の自分の精神状態がシンクロしているようでした」

人の意識は、それまでとは異なる場所、時間、人と出逢い、それらに身を浸すことで初めて深い変化を兆す。人の営みのある街場から剥き出しの自然の中に身体を置いた経験は、石川さんの世界を捉える眼に、なにかしらの影響を与えたのだろうか?
「わかったのは、街も山も変わらないということ。具体的で細かい点は違うけれど、全部が生きてるんだなって。それは凄いことだし怖いことだって」
凄い、という感情は素直に理解できる。でも、怖いって、どういうことなんだ?
「安全や安定なんてどこにもない、っていうことです。生きることは常にギリギリでそれが当たり前。どこかを安定させようすればどこかにズレが生じる。安定って一瞬だけなんですよ。人は生活するのに快適な環境を作ってきたけれど、そのためにどこかが崩れてくる。『食うことと食われることは一緒にあって当然。食っているのだからいつかは食われる』って服部さんも本の中で書いているけれど、山は本当にそのままでした。それは街でも変わらないって思ったんです。人はそのことをわかっているはずなのに、理想でしかない安定した日常が続くことを求めたり、安全とかについて考える。それってどうなんだろうって」
3.11のことを思い浮かべた。安定や安全を得るために、人間は文明を築いてきた。しかし、ある微細な1点のバランスが崩れれば、皮肉にも、自らが作り上げた文明に殺される。5分後どころか1秒後に生きている保証なんてどこにもない。それは冷徹な現実だ。にもかかわらず、僕たちはこの穏やかな日々が未来永劫に渡って続くような幻想に浸って日々を送っている。そのことに対する憤りなのだろうか?
「無自覚に生活している自分たちもクソだし、それでも安全や安定を望まずにはいられなくて、その理想が現実には成り立たないこともクソだ、っていうこと。矛盾しているんですよ」
世界を受け入れるのじゃなくて「引き受ける」のが正しいんじゃないかって思う
「多くの写真家は意味の込もった一枚を求めて、能動的に瞬間を捕えようとします。対して石川竜一は、そこにある状況をいかに写真で受け入れるかということを、撮る行為の核に置く写真家」
これは『絶景のポリフォニー』と『okinawan portraits 2010-2012』、そして『adrenamix』の発行元である赤々舎の代表であり、石川竜一という写真家を最もよく知る人物の1人である姫野希美さんが石川さんを評した文章だ。「受け入れる」は、石川さんを表すキーワードの1つになっている。
しかし、石川さん自身は、この「受け入れる」という言葉に対して常に違和感を感じていたのだという。
「確かに、『目の前にあるものを受け入れるための方法、考えるための手段として写真があってカメラがある』というようなことをこれまで言ってきました。でも、実際は違和感というか、腑に落ちないものがずっとあったんです。そんな折、たまたま読んだサルトルの『嘔吐』の中に、『自分の身に降りかかることを受け入れるのではなく、身に起こることを引き受けること』というフレーズが書かれているのを見つけてからずっと引っかかっていて。受け入れるじゃなくて『引き受ける』のほうが正しいんじゃないかと。受け入れるという言葉を使うことは、僕自身と関係がないように装い過ぎているような感じがするんですよ。イメージとしては、器に無造作に放り込んでいるような感じ。でも、何かを受け入れる時には少なからず感情があって、受け入れているつもりでも無意識に選んでいる部分がある。だから、『引き受ける』という言葉のほうが、意味合いとして正しいんじゃないかと思い始めたんです。まだはっきりとは見えていないので、いまはそれ以上言えません。直感的にですが、これからの自分にとって、この気づきは大きなポイントとなると思っています」

「受け入れる」と「引き受ける」の意味、ニュアンスの違いは、おそらく、他者と向き合うさいの能動性とそこから受ける負荷の違いにある。受け入れることは他者がいさえすればそれで済むが、引き受けるためには深く関わることが避けられない。そこで費やされるカロリーには著しい差がある。
自分一人の表現の壁に突き当たり、写真によって世界とのつながりを回復してきたことが石川さんのこれまでの活動の軌跡だとするならば、さらに踏み込む、つまり、ウォッチャーからアクターへの視点の深化は、まるでそのまま人間の成長のプロセスと重なる。泣くことでしか自分を表現できない赤ちゃんが少年、青年へと育ち、決して綺麗なだけじゃない社会との摩擦の中で大人の男へと成熟してゆくように。
展示会場の最後に、ポラロイドカメラで撮った作品が配置されている。この『考えたときには、もう目の前にはない』という写真展と同名のシリーズは、『絶景のポリフォニー』や『okinawan portraites 2010-2012』と同時期から続く作品で、石川さんの日常身近にある友達や食事といった、生活に根ざした人や物が被写体だ。
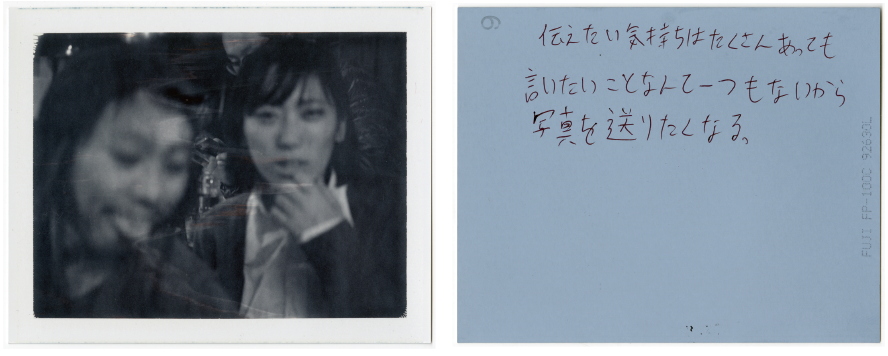
考えたときには、もう目の前にはない/2014~2015年/ピールアパートタイプフィルム
「ポラロイドでは相手と話して、お互いが通じているような空気の中で撮るんです。極私的で親密な関係が写るような。そういうものほど見えないし測れないし、すぐに消えていく。それに、プリントと違って複製できないから同じものは1枚しか残らない。一瞬しか残らないものを撮るのに、ポラロイドは合っていると思いました」
確かに、撮ったその瞬間から、完全に定着することなく、イメージが少しずつ劣化して消えていく、インスタントフィルムの特性に合っている。
「自分のぶんと相手のぶんと、2枚撮るんです。言葉を書いて贈ったりして。ロバート・フランクあたりから始まっているのかな。僕、なんでも写真になればいいと思っているんですよ。でも、その親密さの感情をまだ写真にしていなかったなって思って。いわるゆる「友達写真」ですね。若い子達が「チェキ」で身近なものを撮っているのと同じ」
写真を撮ることは、自分の外の世界を引き受けること。展示会場の最後尾の作品が、インスタントカメラで撮った友達写真というのが石川さんらしい。華々しいデビューから1年、石川さんはいまきっと、次のステージへと上がる階段の1段目に足を掛けようとしているんだ。「にんげーん!」と口に出しながらシャッターを切っていた、という、石川さんの後姿が頭をよぎる。



